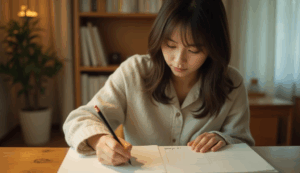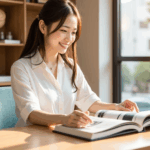故人を偲び、遺族に寄り添う気持ちを表すためのお悔やみの作法には、さまざまな形があります。
香典をお渡しする習慣が一般的ですが、最近ではお花券を贈ることで弔意を示す方も増えてきました。
しかし、いざという時に、お花券をお悔やみでの渡し方について、正しいマナーや相場が分からず戸惑うことも少なくありません。
例えば、お花代としての金額はいくらが適切なのか、いつどのタイミングでお渡しすれば失礼にあたらないのか、また表書きや包み方にはどのような決まりがあるのでしょうか。
さらに、供花とどう違うのか、もし遺族から辞退された場合はどうすれば良いのかなど、疑問は尽きないかもしれません。
この記事では、そうしたお悩みを解消するため、お花券をお悔やみでの渡し方に関するあらゆるマナーを網羅的に解説します。
香典との違いや、郵送する場合の注意点、そしてお悔やみの気持ちをより深く伝えるためのメッセージ文例まで、具体的な情報を丁寧に説明していきます。
また、お花券の代わりとして、またはお花券と合わせて贈ることで、より一層心のこもったお悔やみとなる胡蝶蘭の贈り物についても、その魅力と選び方をご紹介します。
突然の訃報に際しても、慌てずに心のこもった対応ができるよう、ぜひこの記事をお役立てください。
◆胡蝶蘭については、【関連記事】「胡蝶蘭は冠婚葬祭すべてで贈っていい?シーン別のマナーと注意点を解説」と「胡蝶蘭の花言葉とスピリチュアル・風水的な意味|色と置き場所で運気UP」も併せてお読みください。
- お悔やみでのお花券の基本的な渡し方とマナー
- 香典代わりとしてのお花代の適切な相場
- お花券を渡すのにふさわしいタイミング
- 正しい表書きの書き方と包み方のルール
- お花券と供花との明確な違い
- 遺族に配慮したメッセージの文例
- お悔やみの贈り物として胡蝶蘭が選ばれる理由
Contents
🎁 胡蝶蘭を贈るなら通販が便利&安心です!
実は、胡蝶蘭は通販でも高品質なものが手軽に購入できるって知ってました?
贈答用ラッピングや立て札などあなたのご希望に沿った要望にもオプションで対応してくれるショップが多数あります。
※当サイトでおススメの胡蝶蘭専門店をご紹介します!
✅ 【ランノハナドットコム(クマサキ洋ラン農園】
- 農園直送&38年以上の老舗歴:1979年創業以来、ハウスで独自に育成し、自社農園から直送する体制。鮮度と安心感が違います
- 全国花き品評会で金賞受賞の高品質:平成18年度・27年度・30年度の全国花き品評会で金賞を獲得するなど品質重視の実績あり
- 業界最多クラス!7つの無料サービス:無料の高級ラッピング、立札・メッセージカード、配送前の商品画像メール、育て方マニュアル、鉢受け、霧吹きスプレーなど、贈る先にも丁寧な配慮
- 1ヶ月の品質保証付き:配送トラブルや1ヶ月以内に枯れた場合でも、無償で交換対応。品質に絶対の自信を持った保証制度
- 珍しいカラー&品種指定可能、選べる豊富なラインナップ:白・ピンク・イエロー・パープルなど50種以上、大輪・ミディ系、希少なグリーンやパープル品種など豊富に揃う
【公式サイトはこちら】⇒胡蝶蘭専門店『ランノハナドットコム(クマサキ洋ラン農園)』 ![]()
✅ 【胡蝶蘭専門店ギフトフラワー】
- 産地直送で鮮度抜群:契約農園から直接仕入れることで、新鮮な胡蝶蘭を最高の状態でお届け
- 多彩な品揃えと特許技術:定番から「青い胡蝶蘭」「化粧蘭」「金箔蘭」など特許取得商品まで幅広く展開
- 農林水産省金賞・天皇杯受賞の信頼:金賞やブルーリボン賞、天皇杯受賞農園から仕入れており、高品質が保証
- 即日/翌日発送&送料無料:即日発送に対応し、全国ほぼ送料無料(沖縄・北海道は追加送料)
- 会員特典&法人向け請求書払い対応:購入額の2%ポイント付与、法人向けに請求書・領収書発行や支払い方法の柔軟性
【公式サイトはこちら】⇒全国の有名胡蝶蘭が全てある 胡蝶蘭専門店ギフトフラワー ![]()
お花券をお悔やみでの渡し方で知るべき基本マナー
- 香典代わりとしてのお花券の相場は?
- お花券を渡すタイミングと状況
- 表書きや包み方の注意点とは
- 供花との違いと選び方のポイント
- 添えるメッセージに困らないための文例
香典代わりとしてのお花券の相場は?

お悔やみの際に香典の代わりとしてお花券を贈る場合、その相場は香典の金額設定に準じるのが一般的です。
故人との関係性によって金額は変動しますが、基本的な考え方を理解しておくことで、いざという時に迷わずに済むでしょう。
私の経験上、最も重要なのは故人への弔意とご遺族への配慮であり、金額はその気持ちを形にするための一つの目安と捉えるのが良いと思います。
一般的に、友人や会社の同僚、ご近所の方など、一般的なお付き合いの場合は5,000円から10,000円程度が相場とされています。
特にお世話になった方であれば、10,000円から20,000円を包むこともあります。
親族の場合は関係の深さによって大きく異なり、30,000円から100,000円と幅広くなるのが実情です。
これらの金額はあくまで目安であり、ご自身の年齢や社会的立場、地域性によっても変わってくることを念頭に置いてください。
例えば、20代であれば低めの金額でも問題ありませんが、40代以上になると相応の金額を包むことが期待される場合もあります。
お花券は現金とは異なり、直接的すぎない柔らかな印象を与えることができるため、ご遺族の負担を少しでも和らげたいという気持ちを表現するのに適しています。
また、香典を辞退されている場合でも、お花券であれば「お花の代わりに」という形で受け取っていただけるケースも少なくありません。
以下に、故人との関係性に応じたお花券の相場を表にまとめましたので、参考にしてください。
| 故人との関係性 | お花券の相場金額 |
|---|---|
| 祖父母 | 10,000円~50,000円 |
| 両親 | 50,000円~100,000円 |
| 兄弟・姉妹 | 30,000円~50,000円 |
| おじ・おば | 10,000円~30,000円 |
| 友人・知人 | 5,000円~10,000円 |
| 会社の同僚・上司 | 5,000円~10,000円 |
| ご近所の方 | 3,000円~5,000円 |
この表はあくまで一般的な指標です。
最終的には、ご自身の故人への想いやご遺族との関係性を考慮し、無理のない範囲で金額を決定することが何よりも大切ではないでしょうか。
金額の多寡よりも、心を込めてお渡しするという姿勢が、きっとご遺族の心に届くはずです。
お花券を渡すタイミングと状況
お花券をお悔やみでの渡し方において、タイミングは非常に重要です。
ご遺族は大切な方を亡くされ、精神的にも時間的にも余裕がない状況に置かれています。
そのため、相手の負担にならないよう、適切なタイミングを見計らってお渡しすることが、大人のマナーと言えるでしょう。
まず、最も一般的なタイミングは、お通夜や告別式に参列する際です。
受付が設けられている場合は、記帳を済ませた後、受付の方に「御花料」としてお渡しするのがスムーズです。
この際、「この度はご愁傷様でございます」といったお悔やみの言葉を簡潔に述べ、深くお辞儀をすることを忘れないようにしましょう。
もし受付がない場合は、喪主やご遺族に直接お渡しすることになりますが、その際は取り込み中でないか、少し落ち着かれたタイミングを見計らう配慮が必要です。
ご遺族に声をかける際は、「お忙しいところ恐れ入ります」と一言添え、手短にお悔やみを述べてお渡しするのが良いでしょう。
一方で、お通夜や告別式にどうしても参列できない場合もあると思います。
その場合は、後日ご自宅へ弔問に伺うという方法があります。
弔問に伺う際は、必ず事前にご遺族の都合を確認することが鉄則です。
突然訪問すると、かえって迷惑になってしまう可能性があります。
電話で連絡を取り、「ご都合の良い時にお線香をあげさせていただきたいのですが」とご意向を伺いましょう。
弔問の際は、玄関先で簡単にお悔やみを述べてお花券をお渡しし、長居はしないのがマナーです。
また、遠方であったり、ご遺族が弔問を辞退されている場合には、郵送するという選択肢も考えられます。
郵送する際は、現金書留を利用し、お花券だけを送るのではなく、必ずお悔やみの気持ちを綴った手紙を添えるようにしてください。
どのような状況であれ、最も大切なのはご遺族の気持ちを最優先に考えることです。
どのタイミングが最適か迷ったときは、「ご遺族の負担にならないのはいつか」という視点で判断すると、大きな間違いは避けられるでしょう。
故人を悼む気持ちを適切な形で伝えるためにも、渡すタイミングと状況判断は慎重に行う必要があります。
表書きや包み方の注意点とは

お花券をお悔やみで贈る際、その包み方や表書きのマナーは、現金を包む香典の作法に準じます。
これらは故人への敬意とご遺族への配慮を示す重要な要素ですので、細部まで気を配ることが大切です。
まず、お花券を入れる袋は「不祝儀袋(ぶしゅうぎぶくろ)」を使用します。
不祝儀袋には、白黒または双銀の「結び切り」の水引がかかっているものを選びましょう。
「結び切り」は一度結ぶと解けないことから、「不幸が二度と繰り返されないように」という願いが込められています。
反対に、蝶結びの水引は何度も結び直せるため、お祝い事に使用されるものですので、絶対に選ばないように注意してください。
次に、表書きです。
水引の上段中央に、贈る目的を示す「名目」を書きます。
お花券の場合は「御花料(おはなりょう)」または「御花代(おはなだい)」と書くのが一般的です。
これらは宗教・宗派を問わずに使用できるため、相手の宗派が分からない場合でも安心して使えます。
もしキリスト教式であることが分かっている場合は、「お花料」や「献花料(けんかりょう)」と書くとより丁寧です。
表書きを書く際は、薄墨の筆ペンや毛筆を使用するのが正式なマナーです。
薄墨は、「悲しみの涙で墨が薄まってしまった」という気持ちや、「突然のことで墨をする時間がなかった」という弔意を表すものとされています。
水引の下段中央には、自分の氏名をフルネームで書きます。
名目よりも少し小さめの文字で書くと、全体のバランスが良くなります。
夫婦連名の場合は夫の氏名を中央に書き、その左側に妻の名前のみを書きます。
会社関係など3名までの連名であれば、役職が上の人を右から順に書いていきます。
4名以上になる場合は、代表者の氏名を中央に書き、その左側に「外一同(ほか いちどう)」と記し、別紙に全員の氏名を書いて中袋に同封するのがスマートです。
中袋には、表面に包んだ金額を「金◯萬圓」のように旧漢字で書き、裏面には自分の住所と氏名を書きます。
これにより、ご遺族が後で香典返しなどを手配する際に分かりやすくなります。
お花券を中袋に入れる際は、お札と同様に、券の表面が中袋の表側を向くように入れます。
これらの作法は、形式的なものと捉えられがちですが、一つひとつに故人を偲び、ご遺族を気遣う心が込められています。
正しいマナーを実践することで、あなたの深い弔意がより丁寧に伝わることでしょう。
供花との違いと選び方のポイント
お悔やみの際に贈るものとして、「お花券」と似た言葉に「供花(きょうか・くげ)」があります。
これらはどちらもお花に関連するものですが、その意味合いや贈り方には明確な違いがあるため、正しく理解しておくことが重要です。
まず、「お花券」は、その名の通りお花と交換できる商品券です。
これは「御花料」として、香典と同様に現金の代わりに不祝儀袋に包んでご遺族に直接お渡しするものです。
ご遺族は受け取ったお花券を使い、好きなタイミングで好きなお花を購入することができます。
祭壇に飾る花がすでにあふれている場合や、後日改めて仏壇にお花を供えたいと考えているご遺族にとって、非常にありがたい贈り物と言えるでしょう。
一方で、「供花」は、故人への弔意を示すために祭壇の周りに飾られる生花のアレンジメントそのものを指します。
これは、葬儀社や生花店に依頼して、通夜や告別式の会場に直接届けてもらうのが一般的です。
供花は祭壇を華やかに彩り、故人を偲ぶ気持ちを形として表現するもので、会場の統一感を出すために、ご遺族や葬儀社から花の種類や形式が指定されていることもあります。
したがって、供花を贈りたい場合は、まず喪家や葬儀を担当している葬儀社に連絡を取り、贈っても良いか、どのような形式が良いかを確認するのがマナーです。
勝手に手配してしまうと、会場のスペースの問題や、宗教・宗派のしきたりに合わないなどの問題が生じる可能性があるため、注意が必要です。
どちらを選ぶかは、状況やご自身の考え方によって異なります。
- ご遺族の負担を減らし、好きなように使ってほしいと考えるなら「お花券」
- 告別式という場を厳かに彩り、弔意を形として示したいなら「供花」
このように、それぞれの特性を理解した上で選ぶのが良いでしょう。
また、最近では家族葬など小規模な葬儀が増えており、供花や香典を一切辞退されるケースも増えています。
そのような場合でも、後日ご自宅に弔問する際に、ささやかな気持ちとしてお花券をお渡しするのは、ご遺族の負担になりにくく、受け取っていただきやすいかもしれません。
最終的には、ご遺族の意向を尊重することが最も大切です。
訃報の連絡を受けた際に、供花や香典について何か案内があれば、それに従うのが最善の対応となります。
添えるメッセージに困らないための文例

お花券を郵送する場合や、直接お渡しする際に一言添えたいと考えたとき、どのような言葉を選べば良いか迷うことがあると思います。
お悔やみのメッセージは、ご遺族の悲しみに寄り添い、心からの弔意を伝えるためのものです。
長々とした文章はかえって負担になることもあるため、簡潔で心のこもった言葉を選ぶことが大切です。
メッセージを作成する際には、いくつか注意すべき点があります。
まず、「忌み言葉」を避けることです。
「重ね重ね」「たびたび」などの重ね言葉は、不幸が続くことを連想させるため使いません。
また、「死亡」「急死」といった直接的な表現も避け、「ご逝去」「突然のこと」など、より柔らかな言葉に言い換える配慮が必要です。
さらに、ご遺族を励まそうとして「頑張ってください」といった言葉を使うのは、時にプレッシャーを与えてしまうことがあるため、避けた方が賢明です。
ここでは、さまざまな状況で使えるメッセージの文例をいくつかご紹介します。
一般的な文例
「この度は、◯◯様のご逝去の報に接し、心よりお悔やみ申し上げます。
心ばかりのものではございますが、御花料をお送りいたしましたので、御霊前にお供えいただければと存じます。
ご遺族の皆様におかれましても、どうぞご自愛くださいませ。」
親しい友人や知人への文例
「突然のことで、今も信じられない気持ちでいっぱいです。
本来であればすぐにでも駆けつけたいのですが、遠方のため叶わず、申し訳ありません。
ささやかですが、お花代を贈らせていただきます。
どうか無理をしないで、体を大切にしてください。
落ち着いたら、また連絡します。」
職場の同僚や上司のご家族への文例
「ご主人様(奥様)のご逝去を悼み、謹んでお悔やみ申し上げます。
ご生前の笑顔ばかりが思い出され、胸が痛みます。
ささやかではございますが、御花料を同封いたしました。
皆様、さぞお力落としのことと存じますが、くれぐれもご無理なさらないでください。」
これらの文例を参考に、ご自身の言葉で故人への想いやご遺族へのいたわりの気持ちを表現することが、何よりも大切です。
手書きで丁寧に綴ることで、より一層気持ちが伝わるでしょう。
お花券に短いメッセージカードを添えて直接お渡しするのも、とても丁寧な印象を与えます。
その場合は、「心よりお悔やみ申し上げます」といった一言だけでも十分です。
言葉選びに迷ったときは、飾らない素直な気持ちを伝えることを心がけてみてください。
🛒 花言葉や運気を意識した胡蝶蘭ギフトを選ぶには?
通販で胡蝶蘭を選ぶときも、色や用途に応じた花言葉を意識して選ぶと◎です!
🎁 ランノハナドットコム(クマサキ洋ラン農園)
- 農園直送&38年以上の老舗歴:1979年創業以来、ハウスで独自に育成し、自社農園から直送する体制。鮮度と安心感が違います
- 全国花き品評会で金賞受賞の高品質:平成18年度・27年度・30年度の全国花き品評会で金賞を獲得するなど品質重視の実績あり
- 業界最多クラス!7つの無料サービス:無料の高級ラッピング、立札・メッセージカード、配送前の商品画像メール、育て方マニュアル、鉢受け、霧吹きスプレーなど、贈る先にも丁寧な配慮
- 1ヶ月の品質保証付き:配送トラブルや1ヶ月以内に枯れた場合でも、無償で交換対応。品質に絶対の自信を持った保証制度
- 珍しいカラー&品種指定可能、選べる豊富なラインナップ:白・ピンク・イエロー・パープルなど50種以上、大輪・ミディ系、希少なグリーンやパープル品種など豊富に揃う
【公式サイトはこちら】⇒胡蝶蘭専門店『ランノハナドットコム(クマサキ洋ラン農園)』 ![]()
🎁 胡蝶蘭専門店オーキッドファン
- 生産者直送・高品質:埼玉などの世界洋蘭展・ブルーリボン賞受賞農園と直取引し、受賞歴ある生産者が育てた胡蝶蘭を提供
- 即日?翌日全国配送対応:平日13時までの注文で、本州・四国なら翌日のお届けに対応。一部商品は当日配送も可能
- ラッピング&写真送信サービス:ラッピング無料。さらに有料オプションで、実際に発送した胡蝶蘭の画像を注文者にメールで送ってもらえる
- 支払い方法が豊富で法人対応もOK:クレジット・銀行振込・楽天ペイ・ビットコイン支払いに加え、法人向けに後払い(請求書払い)にも対応(審査あり)
- 送料無料・送料明快+JCB商品券プレゼント:本州・四国は送料無料、北海道・九州は1,080~3,240円、沖縄は3,240~4,320円。さらに大輪胡蝶蘭注文で1,000円分のJCB商品券プレゼントあり
【公式サイトはこちら】⇒胡蝶蘭専門店オーキッドファン ![]()
迷わず贈れるお花券をお悔やみでの渡し方の知識
- お花代として贈る際の封筒の選び方
- 失礼にあたらない金額設定のコツ
- 遺族が辞退された場合の対応方法
- 現金書留で郵送する際のマナー
- 贈り物として胡蝶蘭を選ぶ理由
- お花券をお悔やみでの渡し方の総まとめ
お花代として贈る際の封筒の選び方

お花券をお悔やみで贈る際、お花券そのものだけでなく、それ入れる封筒の選び方にもマナーがあります。
これは、ご遺族に対して敬意を払い、弔意を正しく伝えるための大切なステップです。
基本的には、香典で現金をお包みする時と同じ「不祝儀袋」を用いるのが正解です。
コンビニエンスストアや文房具店、スーパーマーケットなどで手軽に購入できますが、いくつか種類があるため、状況に応じて適切なものを選ぶ必要があります。
まず、最も重要なのが「水引」の種類です。
弔事用の水引は、白黒または双銀の「結び切り」や「あわじ結び」のものを選びます。
これらは固く結ばれていて簡単に解けないことから、「不幸を繰り返さない」という意味が込められています。
お祝い事で使われる「蝶結び」は絶対に使用してはいけません。
次に、包む金額によって不祝儀袋の格が変わることも覚えておきましょう。
- 5,000円程度まで:水引が印刷されたタイプのシンプルな封筒
- 10,000円~30,000円程度:白黒の結び切りの水引がかけられた一般的なタイプ
- 50,000円以上:双銀の水引がかけられた、より高級感のある大判のタイプ
包む金額と袋の格が見合っていないと、かえって失礼にあたることがあるため注意が必要です。
金額に見合った適切な不祝儀袋を選ぶことが、相手への配慮を示すことにつながります。
また、宗教・宗派によっても適した不祝儀袋が異なります。
仏式の場合、蓮の花が描かれたデザインの不祝儀袋が使われることがありますが、これは浄土真宗以外の仏式で用いられるものです。
相手の宗派が分からない場合は、蓮の花が描かれていない無地のものを選ぶのが最も無難です。
キリスト教式の場合は、水引のない白い封筒や、十字架や百合の花が描かれた専用の封筒を使用します。
もし相手の宗教が不明な場合は、やはり水引のない無地の白い封筒か、白黒結び切りのシンプルな不祝儀袋を選び、「御花料」と表書きしておけば、どの宗教でも失礼にはあたりません。
お花券を購入した際に、専用の封筒やケースが付いてくることもありますが、それらはあくまで贈答用であることが多いです。
お悔やみの場面では、それらをそのまま使うのではなく、改めて不祝儀袋に入れ替えるのが丁寧な対応と言えるでしょう。
封筒一つをとっても、そこには日本の深い文化と相手を思いやる心が反映されています。
適切な封筒を選ぶことで、あなたの弔意はより深く、そして正しく伝わるはずです。
失礼にあたらない金額設定のコツ
お花券をお悔やみで贈る際の金額設定は、多くの方が悩むポイントの一つです。
相場は前述の通りですが、それ以外にも失礼にあたらないためのいくつかのコツが存在します。
これらは、日本の慣習や相手への心遣いに基づくもので、知っておくとよりスマートな対応ができます。
まず、日本では「偶数」の金額は「割り切れる」ことから「故人との縁が切れる」ことを連想させるため、避けるべきとされています。
したがって、2万円や4万円といった金額は避けるのが一般的です。
ただし、偶数の中でも「2」はペアを意味することから問題ないとされる場合もありますが、迷った場合は奇数の金額(1万円、3万円、5万円など)を選ぶのが無難でしょう。
また、数字の「4(死)」や「9(苦)」は、直接的に不吉なことを連想させるため、これらの数字がつく金額(例:4,000円、9,000円)は絶対に避けるべきです。
これは金額設定における絶対のタブーと心得ておきましょう。
次に、お花券や現金を用意する際には、新札を避けるというマナーがあります。
新札は、前もって準備していたような印象を与え、「不幸を予期していた」と受け取られかねないためです。
手元に新札しかない場合は、一度折り目を付けてから包むようにしましょう。
この一手間が、ご遺族への配慮の表れとなります。
かといって、あまりにも使い古されたお札や、破れていたり汚れていたりするお札は失礼にあたりますので、適度に綺麗な、しかし新札ではないお札を選ぶのが理想的です。
お花券の場合は、このマナーは厳密に適用されませんが、念のため覚えておくと良いでしょう。
また、金額を決定する際には、周囲の人と相談するのも一つの方法です。
例えば、職場の同僚の家族が亡くなった場合、他の同僚や上司と相談し、連名で贈ったり、金額を合わせたりすることで、一人だけ突出して高額または低額になるのを防ぐことができます。
これにより、ご遺族に余計な気遣いをさせることもありません。
最終的に最も重要なのは、ご自身の経済状況を鑑み、無理のない範囲で心を込めて贈ることです。
高額な金額を包むことだけが弔意の表現ではありません。
むしろ、無理をして高額を包むことは、今後の人間関係においてもお互いの負担になりかねません。
これらのコツを踏まえ、故人への感謝や哀悼の気持ち、そしてご遺族へのいたわりの心を金額という形に託すことが、失礼にあたらない金額設定の本質と言えるのではないでしょうか。
遺族が辞退された場合の対応方法

近年、家族葬の増加や価値観の多様化に伴い、ご遺族の意向で香典や供花、供物などを一律に辞退されるケースが増えています。
訃報の連絡を受けた際に、「誠に勝手ながら、御香典、御供花、御供物の儀は固くご辞退申し上げます」といった文言があった場合は、その意向を尊重することが最も大切なマナーです。
このような場合に、無理にお花券や香典を渡そうとすることは、かえってご遺族の負担を増やし、困惑させてしまうことになりかねません。
「何かしないと申し訳ない」という気持ちは分かりますが、まずはご遺族の気持ちを最優先に考え、何もしない、という選択をすることが最善の弔意となります。
お通夜や告別式に参列する際は、受付で「ご遺族様のご意向に沿い、お持ちいたしませんでした」と伝え、記帳だけを済ませるのがスマートな対応です。
しかし、どうしても弔意を形として表したいという場合、どうすれば良いのでしょうか。
一つの方法として、後日、ご遺族が少し落ち着かれた頃を見計らって、お悔やみの手紙を送るという方法があります。
手紙であれば、ご遺族に返礼などの気遣いをさせることなく、故人を悼む気持ちやご遺族をいたわる気持ちを静かに伝えることができます。
その際に、高価な品物を同封するのは避けましょう。
また、別の方法として、お花券のようにかさばらず、後日ご遺族が好きな時に使えるものであれば、受け取ってもらえる可能性もゼロではありません。
ただし、これも相手の状況をよく考える必要があります。
もし後日弔問に伺う機会があれば、その際に「ささやかですが、お好きなお花でもお供えください」と、控えめに、そして相手が断りやすいような形で差し出してみるのも一つの手です。
もし、それでも「お気持ちだけで」と辞退された場合は、決して無理強いせず、速やかに引き下がりましょう。
「承知いたしました。では、お言葉に甘えさせていただきます」と笑顔で応じ、その場を辞することが大切です。
重要なのは、ご遺族の「辞退する」という決断の裏には、「参列してくださる方々に余計な負担をかけたくない」「香典返しなどの手間を省きたい」といった、深い配慮があることを理解することです。
その気持ちを汲み取り、その意向に従うことこそが、真の意味でご遺族に寄り添うことにつながるのです。
弔意の示し方は一つではありません。
ご遺族の状況と気持ちを尊重した行動を心がけましょう。
現金書留で郵送する際のマナー
遠方に住んでいたり、やむを得ない事情で通夜や告別式に参列できない場合、お花券や香典を郵送するという方法があります。
その際、普通郵便や宅配便で送るのはマナー違反であり、必ず郵便局の「現金書留」を利用するのが鉄則です。
現金書留は、万が一の郵便事故の際に損害額が賠償されるため、大切な弔慰金を安全に届けるための唯一の方法と言えます。
現金書留で送る際には、いくつかのマナーと手順があります。
まず、郵便局で現金書留専用の封筒を購入します。
この封筒に、不祝儀袋に入れたお花券(または現金)と、お悔やみの手紙を同封します。
お花券だけ、あるいは現金だけを無言で送りつけるのは大変失礼にあたります。
なぜ参列できないのかという理由と、故人を悼む気持ち、ご遺族を気遣う言葉を綴った手紙を必ず添えましょう。
これが郵送する際における最も重要なマナーです。
宛名は、喪主様のお名前で送るのが基本です。
もし喪主様のお名前が分からない場合は、「(故)◯◯様 ご遺族様」としても問題ありません。
送るタイミングも重要です。
あまり早すぎると、ご遺族が葬儀の準備で大変な時期に届いてしまい、かえって手間をかけてしまう可能性があります。
告別式が終わってから2〜3日後、少し落ち着かれた頃から、遅くとも初七日までには届くように手配するのが一般的です。
もしそれよりも遅くなってしまった場合は、四十九日までに送るようにし、手紙には遅れたことへのお詫びを一言添えると丁寧です。
以下に、現金書留で送る際の手順をまとめます。
- 不祝儀袋を用意し、表書きと氏名を書く。中袋にも金額、住所、氏名を記入し、お花券を入れる。
- お悔やみの手紙を書く。便箋は白無地などのシンプルなものを選び、時候の挨拶は省いて本題から書き始める。
- 郵便局で現金書留封筒を購入し、宛名と差出人を記入する。
- 封筒に不祝儀袋とお悔やみの手紙を入れ、封をして割り印(または署名)をする。
- 郵便局の窓口に提出し、料金を支払う。
これらの手順とマナーを守ることで、直接お会いできなくても、あなたの深い弔意と敬意はきちんとご遺族に伝わります。
物理的な距離があっても、心を寄せる気持ちを丁寧に形にすることが大切です。
贈り物として胡蝶蘭を選ぶ理由

お悔やみの気持ちを伝える方法は、お花券や香典だけではありません。
特に、品格があり、心のこもった贈り物として「胡蝶蘭(こちょうらん)」を選ぶ方が増えています。
なぜ、数ある花の中でも胡蝶蘭がお悔やみの場にふさわしいとされているのでしょうか。
それには、いくつかの明確な理由があります。
まず第一に、その花言葉です。
胡蝶蘭には「純粋な愛」「清純」といった花言葉があり、故人への清らかな愛情や尊敬の念を表すのに非常に適しています。
また、蝶が舞うような花の形から「幸福が飛んでくる」という縁起の良い意味合いもあり、これは「故人が安らかに旅立ち、ご遺族に平穏が訪れますように」という願いにも通じます。
第二に、その見た目の上品さと格調高さです。
胡蝶蘭の凛とした佇まいは、厳粛な雰囲気が求められるお悔やみの場にふさわしく、祭壇やご自宅の仏壇の周りを、派手すぎず、しかしながらも気品高く彩ります。
特に、白の胡蝶蘭は清らかさと哀悼の意を象徴する色として、最も一般的に選ばれています。
第三の理由として、実用的な側面が挙げられます。
胡蝶蘭は花粉や香りがほとんどないため、アレルギーの心配がある方や、花の強い香りが苦手な方、また病院や施設へ贈る場合でも安心して選ぶことができます。
さらに、花持ちが非常に良く、適切な管理をすれば1ヶ月以上も美しい花を咲かせ続けます。
葬儀後の慌ただしい日々の中で、ご遺族が寂しさを感じる時期にも、静かに寄り添い、心を慰めてくれる存在となるでしょう。
水やりの手間も少ないため、悲しみの中にいるご遺族に余計な負担をかけないという点も、大きなメリットです。
お花券をお渡しする際に、併せて小さな胡蝶蘭の鉢植えを贈ったり、香典や供花を辞退されている場合に、後日ご自宅へ胡蝶蘭をお届けしたりするのも、非常に心のこもった弔意の表し方です。
お花券がご遺族の自由を尊重する贈り物であるとすれば、胡蝶蘭は故人を偲び、ご遺族の心を癒やす「時間」を贈るものと言えるかもしれません。
もし、お悔やみの贈り選びに迷われたなら、故人への敬意とご遺族への深い思いやりを同時に示すことができる胡蝶蘭を、選択肢の一つとして考えてみてはいかがでしょうか。
お花券をお悔やみでの渡し方の総まとめ
これまで、お花券をお悔やみでの渡し方に関するさまざまなマナーや知識について詳しく解説してきました。
突然の訃報に際し、故人を悼み、ご遺族に寄り添う気持ちをどのように表せばよいか、戸惑うことは誰にでもあることです。
お花券は、香典の代わりとして、またはそれに代わる新しい弔意の形として、多くの場面で役立つ選択肢となります。
重要なポイントを振り返ってみましょう。
まず、相場は故人との関係性によって決まり、香典の金額に準じるのが基本です。
渡すタイミングは、お通夜や告別式の受付が一般的ですが、後日の弔問や郵送という方法もあります。
その際は、必ずご遺族の都合を最優先に考えることが大切です。
表書きは「御花料」とし、薄墨で書くのがマナーです。
不祝儀袋は金額に見合ったものを選び、水引は白黒の結び切りを用いることを忘れないでください。
また、ご遺族が香典などを辞退されている場合は、その意向を尊重し、無理に渡そうとしないことが最大の配慮となります。
もし郵送する場合は、必ず現金書留を利用し、心を込めたお悔やみの手紙を添えることで、あなたの気持ちはより深く伝わるでしょう。
そして、お花券という選択肢に加え、贈り物として胡蝶蘭を選ぶことも、非常に thoughtful な方法です。
その気品ある佇まいと、ご遺族に負担をかけない特性は、あなたの深い哀悼の意を静かに、そして長く伝え続けてくれます。
結局のところ、お花券をお悔やみでの渡し方における全てのマナーの根底にあるのは、「故人を敬い、ご遺族を思いやる心」です。
形式や作法は、その心を相手に正しく伝えるための手段にすぎません。
この記事でご紹介した知識が、あなたのその大切な気持ちを、適切な形で届けるための一助となれば幸いです。
いざという時に、自信を持って、そして心からの弔意を示せるよう、これらのポイントを心に留めておいていただければと思います。
- お花券は香典代わりとしてお悔やみで贈ることができる
- 相場は故人との関係性で決まり5千円から10万円と幅広い
- 渡すタイミングは通夜や告別式または後日の弔問が良い
- 不祝儀袋に入れ表書きは「御花料」と薄墨で書くのが作法
- 水引は白黒の「結び切り」を選び不幸が続かない願いを示す
- お花券はご遺族が好きな花を選べるという利点がある
- 供花は祭壇に飾る生花そのものであり葬儀社経由で手配する
- ご遺族が香典などを辞退した場合はその意向を尊重する
- 郵送する際は現金書留を使い必ずお悔やみの手紙を添える
- 金額は偶数や4と9を避け新札でないものが望ましい
- 添えるメッセージでは忌み言葉を避け簡潔に気持ちを伝える
- お花券の代わりに品格のある胡蝶蘭を贈るのも良い選択肢
- 胡蝶蘭は花粉や香りが少なく花持ちが良いため負担が少ない
- 白い胡蝶蘭は「清純」という花言葉を持ちお悔やみに最適
- 全てのマナーの基本は故人を偲び遺族を気遣う心である
胡蝶蘭専門店おすすめランキング
【ランノハナドットコム(クマサキ洋ラン農園)】
- 農園直送&38年以上の老舗歴:1979年創業以来、ハウスで独自に育成し、自社農園から直送する体制。鮮度と安心感が違います
- 全国花き品評会で金賞受賞の高品質:平成18年度・27年度・30年度の全国花き品評会で金賞を獲得するなど品質重視の実績あり
- 業界最多クラス!7つの無料サービス:無料の高級ラッピング、立札・メッセージカード、配送前の商品画像メール、育て方マニュアル、鉢受け、霧吹きスプレーなど、贈る先にも丁寧な配慮
- 1ヶ月の品質保証付き:配送トラブルや1ヶ月以内に枯れた場合でも、無償で交換対応。品質に絶対の自信を持った保証制度
- 珍しいカラー&品種指定可能、選べる豊富なラインナップ:白・ピンク・イエロー・パープルなど50種以上、大輪・ミディ系、希少なグリーンやパープル品種など豊富に揃う
【胡蝶蘭専門店ギフトフラワー】
- 産地直送で鮮度抜群:契約農園から直接仕入れることで、新鮮な胡蝶蘭を最高の状態でお届け
- 多彩な品揃えと特許技術:定番から「青い胡蝶蘭」「化粧蘭」「金箔蘭」など特許取得商品まで幅広く展開
- 農林水産省金賞・天皇杯受賞の信頼:金賞やブルーリボン賞、天皇杯受賞農園から仕入れており、高品質が保証
- 即日/翌日発送&送料無料:即日発送に対応し、全国ほぼ送料無料(沖縄・北海道は追加送料)
- 会員特典&法人向け請求書払い対応:購入額の2%ポイント付与、法人向けに請求書・領収書発行や支払い方法の柔軟性
【胡蝶蘭専門店オーキッドファン】
- 生産者直送・高品質:埼玉などの世界洋蘭展・ブルーリボン賞受賞農園と直取引し、受賞歴ある生産者が育てた胡蝶蘭を提供
- 即日?翌日全国配送対応:平日13時までの注文で、本州・四国なら翌日のお届けに対応。一部商品は当日配送も可能
- ラッピング&写真送信サービス:ラッピング無料。さらに有料オプションで、実際に発送した胡蝶蘭の画像を注文者にメールで送ってもらえる
- 支払い方法が豊富で法人対応もOK:クレジット・銀行振込・楽天ペイ・ビットコイン支払いに加え、法人向けに後払い(請求書払い)にも対応(審査あり)
- 送料無料・送料明快+JCB商品券プレゼント:本州・四国は送料無料、北海道・九州は1,080~3,240円、沖縄は3,240~4,320円。さらに大輪胡蝶蘭注文で1,000円分のJCB商品券プレゼントあり